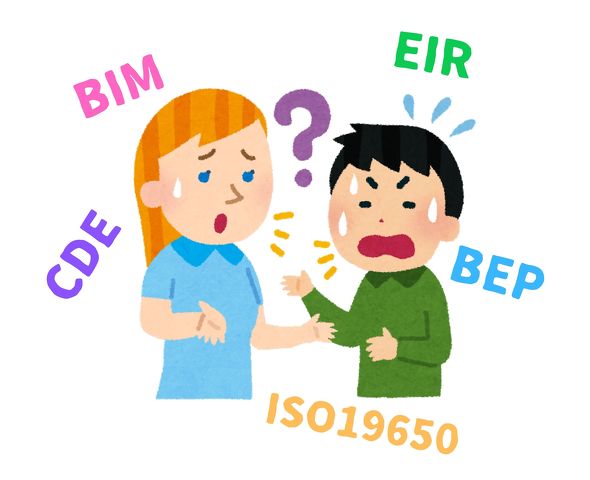間違いだらけの「日本のBIMの常識」Vol.1 そもそもBIMとは何か?【日本列島BIM改革論:Reboot】:日本列島BIM改革論〜建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ(10)(1/4 ページ)
日本では誤解された「BIMの解釈」がまん延しており、それが日本と海外の差を生んでいる。このままでは日本のBIMは正しく成長できず、迷走する可能性がある。正しいBIMの常識とは何か、いくつかの用語について正しく理解しておこう。
間違っている日本のBIMの常識とその弊害
日本のBIMは基本的に技術志向で、BIMソフトウェアの利用方法として、プレゼンテーションや干渉チェックなどのBIMモデルの3次元形状を活用した取り組みは、一定の成果を出している。
しかし、BIMに対して国際規格を含む海外の常識は、日本と異なり、大きなギャップとなっている。海外や国際規格でのBIMは技術志向ではなく、“プロセス志向”といえる。設計・施工のプロセスを見直し、全ての情報を対象とした情報マネジメントにより、情報の統合とデジタル化を目指すという動きに代わってきている。
志向のギャップの根底には、BIMに関する重要な概念に対し、日本独自の解釈や誤解や用が深く関わっているのではないか。「BIM」「CDE(共通データ環境)」「EIR(情報交換要求事項)」「BEP(BIM実行計画)」といった最も基本的な用語でさえ、国際標準に基づく意味合いからは大きく逸脱して解釈されていることが多い。
★連載バックナンバー:
『日本列島BIM改革論〜建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ〜』
日本の建設業界が、現状の「危機構造」を認識し、そこをどう乗り越えるのかという議論を始めなければならない。本連載では、伊藤久晴氏がその建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオを描いてゆく。
こうした誤解や運用のズレは、BIMの真価を生かせる仕組みの構築を阻害し、日本の建設業界全体の生産性向上や国際競争力の向上を遅らせる要因となっている。表面的には「BIMを導入した」としながらも、実態は海外の先進事例が重視する「発注組織主導の情報マネジメント」や「データドリブンな意思決定支援」の領域には遠く及ばない。BIMが単なる技術ではなく、文化や組織の在り方そのものを変える取り組みだと、日本で十分に認識されていないことに起因する。そのため、日本と海外の差は開いていく一方だ。
さらに問題を深刻化させているのは、技術志向の取り組みなのに、「フロントローディング」「生産性向上」「コストの削減」といった美辞麗句だけが独り歩きしている点がある。こうしたキーワードは確かに重要だが、実現には、まず情報の正確な流れの確立と、それを支える責任分担の明確化が欠かせない。単に3Dモデルを作成することにとどまらず、ISO 19650など国際標準の考え方に沿って、「情報マネジメント」を構築する覚悟が求められる。
現状のままでは、いくらBIMを導入しても部分的/短期的な成果しか得られず、結果として「BIMは意味がない」「BIMは使えない」と誤解される悪循環に陥ってしまう。BIMが本来目指す「ライフサイクル全体での情報価値の最大化」「発注者、設計者、施工者、運用者間の協働による全体最適化」を真に実現するには、用語の正確な理解にとどまらず、その背景にある考え方まで踏み込む必要がある。決して簡単なことではないが、逆に言えばそこに踏み込まない限り、日本のBIMは国際的な潮流や先進事例に追いつけないままであり続ける。
そこで今回は、海外や国際規格と比べ、日本の多くの方が勘違いしていると思われる最も基本となる4つのBIM関連の用語について説明してみたい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事トップ10
- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験
- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat
- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開
- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化
- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】
- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証
- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定
- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー
- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化
- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ