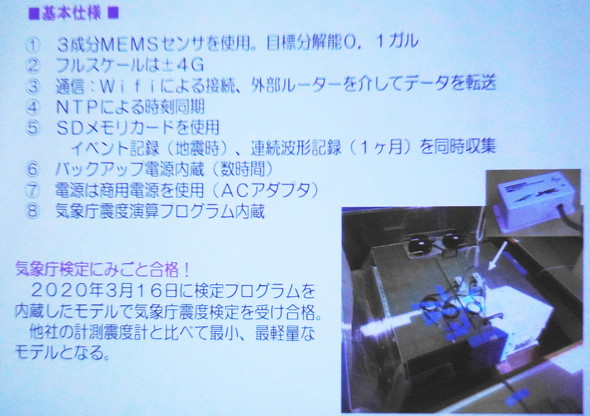ニュース
特定地域の地盤や建物が地震でどれだけ揺れるか調査可能な新サービス:製品動向(3/3 ページ)
地域微動探査協会は、地盤と建物ごとに、地震波の周期や増幅の特性を調べられるサービス「常時微動探査法」と「ハイブリッド微動探査」を開発した。
安全性レポートや耐震性補強に役立つデータを提供
梶原氏は、南海トラフと首都直下の地震で被害を受けやすいエリアにある戸建てを対象に2020年10月から提供を開始するサービスについて、「リフォーム会社と連携して、両地域にある住宅1000棟限定で、地震計を取り付け、地震発生時の状況をモニタリングする。その後、収集したデータに基づき、レポートを作成し、住民に提供する。住民にとっては、地震後に建物の状態を把握できるとともに、気象庁発表の震度と住居の揺れなどが比べることで、早期の地震対策を図れるようにもなる」とコメントした。
サービスの流れは、まず、高性能振動計で対象地盤と住宅の耐震性を調べた後、必要に応じて、リフォーム会社が住宅を補強する。地震計を建物に設置し、モニタリングをスタートして、地震が起きた際にはリアルタイムに被災度を測る。地震時もしくは1カ月に1回安全性レポートを発行し、モニタリング開始から5〜10年後に、高性能振動計を用いた建物の再評価サービスを提案する。
価格は、常時微動探査法が10万円で、ハイブリッド微動探査は8〜10万円、地震時に住宅の状況をモニタリングするサービスは15万円(いずれも税別)。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 大成建設がMSと協業、初手は地震による建物への影響や作業員の現状などを“見える化”
大成建設がMSと協業、初手は地震による建物への影響や作業員の現状などを“見える化”
大成建設は、運用・保守事業も行える体制を整備し、これまでの建物の引き渡しだけでなく、建造物のライフサイクル全体を収益元の対象とするストック型ビジネスの展開を検討している。 地震データの改ざんを防ぐ、“ブロックチェーン”を活用した地震被害のシミュレーションの開発に着手
地震データの改ざんを防ぐ、“ブロックチェーン”を活用した地震被害のシミュレーションの開発に着手
不動産テックのツバイスペースが、建築テック業界を対象に、地震データの改ざん防止を担保しつつ、AIを使って、地震の被害シミュレーションを可能にする画期的なシステムの商用サービス開発に乗り出した。 戸田建設が開発した加速度センサーを用いた地震モニタリングシステムを公共施設に初導入
戸田建設が開発した加速度センサーを用いた地震モニタリングシステムを公共施設に初導入
戸田建設は、自社開発の地震モニタリングシステム「ユレかんち」を東京都の東久留米市にある生涯学習センターに設置した。公共施設に設置した初めての導入事例となる。 地震モニタリングシステム開発、無線加速度センサーで導入費用を大幅削減
地震モニタリングシステム開発、無線加速度センサーで導入費用を大幅削減
大成建設は、地震発生直後の各建物の状況を評価した情報を被災履歴などともにクラウド上で管理できるモニタリングシステムを開発した。災害時に事業継続や復旧を図るためのBCP支援ツールとして展開していく。