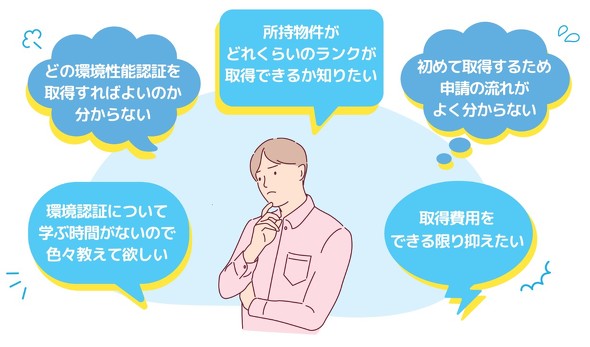BELS、CASBEE、DBJ GB…環境性能認証は不動産の“必須要件”になるか(後編):「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(3)(2/2 ページ)
本連載では、環境・省エネルギー計算センター 代表取締役の尾熨斗啓介氏が、省エネ基準適合義務化による影響と対応策、建築物の環境認証などをテーマに執筆。第3回は建築物の環境性能認証について、認証を選ぶ際の判断基準や外注先選定のポイントを解説します。
外注先を選ぶ際のポイント
環境性能認証の取得を代行するのは、「省エネ計算会社」「不動産コンサルティング会社」「不動産鑑定会社」「金融機関」などの企業です。この中でも実際に認証取得に対応できる企業はまだ限られており、対応範囲もそれぞれ異なります。外注先は慎重に見極めて選定する必要があります。
例えば、認証取得の際に目標とするランクを設定しても、物件の条件によっては達成が難しい場合もあります。実際に省エネ計算を行ってみないと判断できないことが多いのですが、仮に希望ランクが取得できない場合でも、計算を行えば当然費用は発生してしまいます。
このような事態を避けるには、まずは最低限の計算で希望ランクでの取得可否を判別する「スクリーニング」を行えば、費用負担を最小限に抑えられます。しかし、スクリーニングが可能な会社は多くありません。
「どの物件にどの環境性能認証が適しているか分からない」といった悩みを解決するには、複数の環境性能認証に精通した企業に相談するのが有効です。特定の環境性能認証にしか対応していない企業に依頼した場合、より高いランクの取得が見込める他の認証が選択肢に入らず、ESG対応や不動産価値の向上といった本来の目的を果たせなくなるおそれがあります。
その点、複数の環境性能認証に対応できる企業であれば、物件の特性に応じた最適な認証の提案から、スクリーニング、取得までをしっかりサポートしてくれる可能性が高いでしょう。
一方で、中には申請手続きだけを請負い、その他の業務は全て依頼者側に任せるケースも存在します。申請状況の報告や必要な説明が不十分で、依頼者側が不安を感じることもあるようです。
つまり、外注先を選ぶポイントとして、認証取得に関する実績が豊富なこと、専門知識を要する作業を全て任せられる体制が整っていることが挙げられます。「どの環境性能認証を取得すればいいのか」「目標ランクの達成が可能か」「費用を抑える方法はあるのか」といった相談に応じてもらえるかも重要です。
実績はWebサイトなどで公表していたり、契約上の理由で公表していなかったりします。適切な外注先を見極めるには、手間かもしれませんが、複数の企業に問い合わせて相談した上で、比較検討するのが確実です。
著者Profile
尾熨斗 啓介/Keisuke Onoshi
環境・省エネルギー計算センター(運営会社:HorizonXX)代表取締役。
日本大学 理工学部 建築学科、日本大学大学院 理工学研究科 不動産科学専攻卒業後、大手日系証券会社に入社。不動産ファンドアレンジメントやREIT主幹事業務に従事する。その後、大手外資系証券会社で同様の業務に従事。2012年に独立し、HorizonXX(ホライズン)代表取締役に就任。2019年に「環境・省エネルギー計算センター」のビジネスを開始。
現在、建築物の省エネ性能が基準を満たしているかどうか調べる「省エネ計算業務」を引き受け、国の政策推進に貢献する「環境設計士」という新たな職業の確立を目指し、年間約1000件の省エネ計算/環境性能認証取得サポートを請け負う。
近著に『環境性能認証に対応できる「不動産・建築ESG」実践入門』(日本実業出版社)。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 産業動向:新築注文住宅で工事中の施工不良50%超え、さくら事務所の検査で判明
産業動向:新築注文住宅で工事中の施工不良50%超え、さくら事務所の検査で判明
さくら事務所は2024年1月〜12月、新築注文住宅265件で工事中の第三者住宅診断を実施し、その検査結果を集計したところ、全ての検査項目で不具合指摘率が50%を超えていた。 パナソニック電材事業の重要拠点ベトナム視察:日本の70年代を彷彿とさせるベトナム パナソニック現地法人が電材など30年で売上高222億円
パナソニック電材事業の重要拠点ベトナム視察:日本の70年代を彷彿とさせるベトナム パナソニック現地法人が電材など30年で売上高222億円
パナソニックのベトナム工場は、日本品質の電設資材や照明、室内空調機器の製造拠点として重要な役割を担っている。2014年の稼働開始以降、増築や新棟の建設に加え、生産プロセスでも自動化と内製化を進め、生産能力を強化。配線器具は従来の月産900万台から2030年度までに約1.8倍となる月産1600万台の量産体制を整備する。 リノベ:築48年の社宅が一棟丸ごとZEH水準の賃貸マンションに再生、奥村組
リノベ:築48年の社宅が一棟丸ごとZEH水準の賃貸マンションに再生、奥村組
奥村組の築48年の社宅をリノベーションした全住戸ZEH水準の賃貸マンション「OC RESIDENCE R NISHINOMIYA OGO」が竣工した。 ZEH:ZEH水準を上回る省エネ性能の「GX志向型住宅」に対応、ミサワホーム
ZEH:ZEH水準を上回る省エネ性能の「GX志向型住宅」に対応、ミサワホーム
ミサワホームの木質系工業化住宅と耐震木造住宅商品が、ZEH水準を上回る省エネ性能を持つ「GX志向型住宅」に対応した。 産業動向:都が4月に「太陽光パネル義務化」 設置有り無しマンションで4968万円もの差、LIFULL HOME'Sが調査
産業動向:都が4月に「太陽光パネル義務化」 設置有り無しマンションで4968万円もの差、LIFULL HOME'Sが調査
LIFULL HOME'Sは、2025年4月から始まる東京都の太陽光発電の設置義務化に先立ち、気になる現状と今後を調査した。その結果、太陽光パネル設置物件は賃貸や戸建てで全国的に増加しているが、マンションは2024年までは減少傾向にあると判明した。住宅価格は、マンションで太陽光パネル設置有り無しで4968万円もの差額があり、条例施行によりさらなる高騰が懸念される。 「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(1):“着工難民”発生の懸念も 4月施行の「建築物省エネ法」を専門家が徹底解説【新連載】
「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(1):“着工難民”発生の懸念も 4月施行の「建築物省エネ法」を専門家が徹底解説【新連載】
本連載では、建築物の省エネ計算や省エネ適合性判定、近年関心が高まる環境認証取得サポートなどを手掛ける「環境・省エネルギー計算センター」代表取締役の尾熨斗啓介氏が、省エネ基準適合義務化による影響と対応策、建築物の環境認証などをテーマに執筆。第1回は、施行まで1カ月を切った「改正建築物省エネ法」についてこれまでの建築物省エネ化の経緯も踏まえつつ解説する。